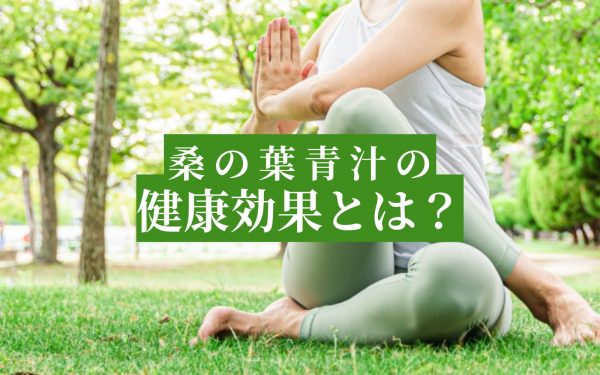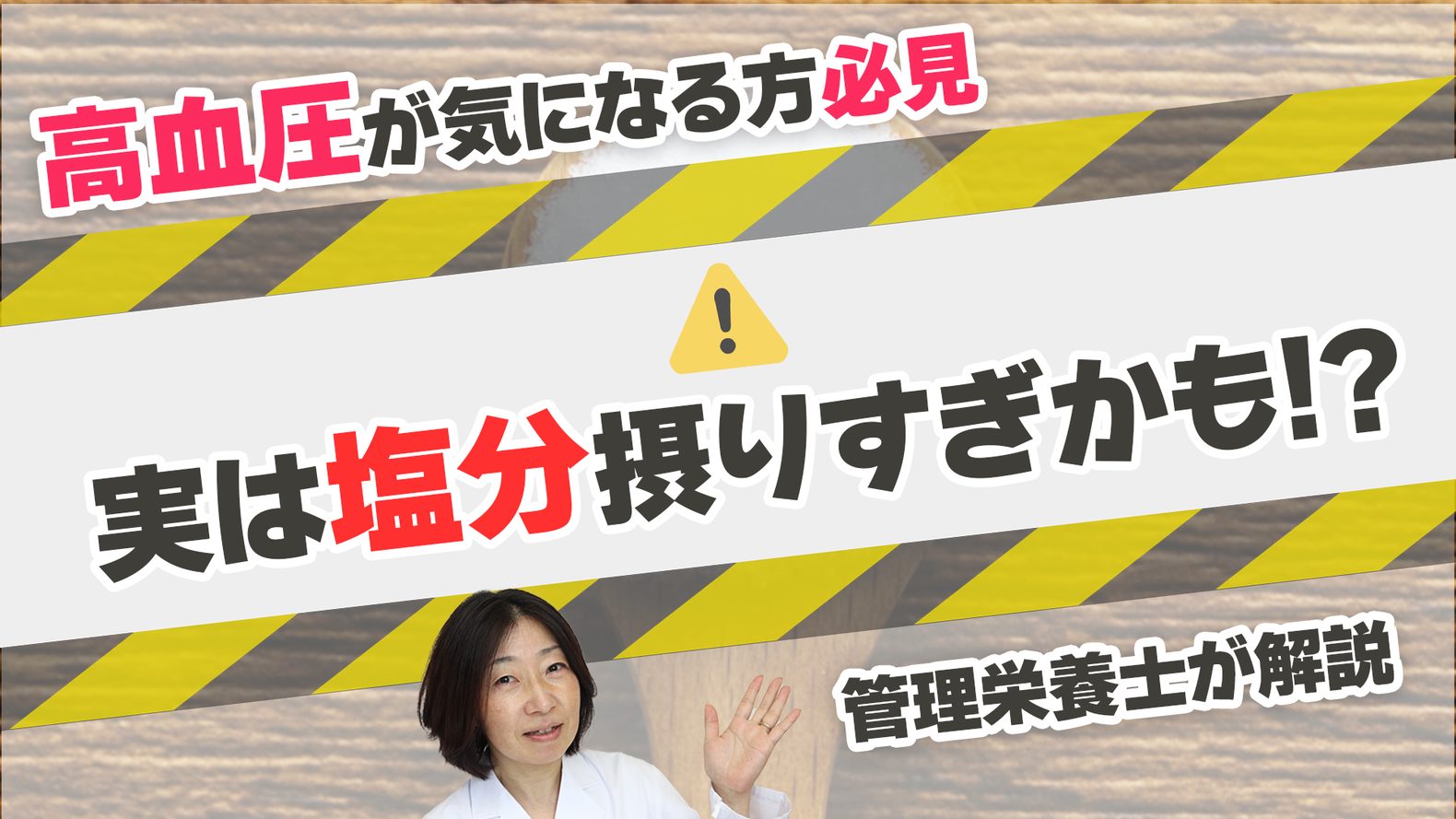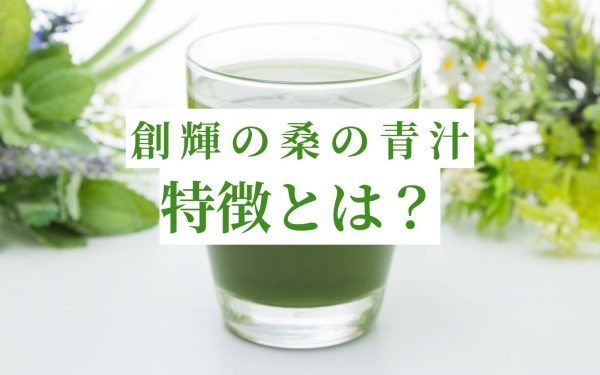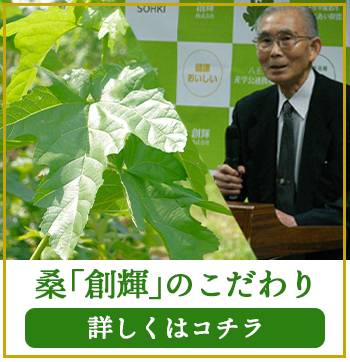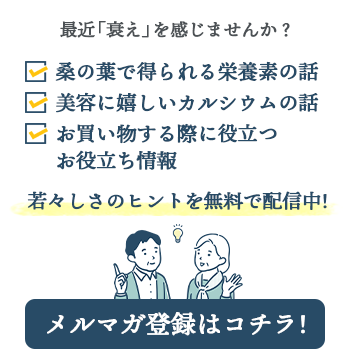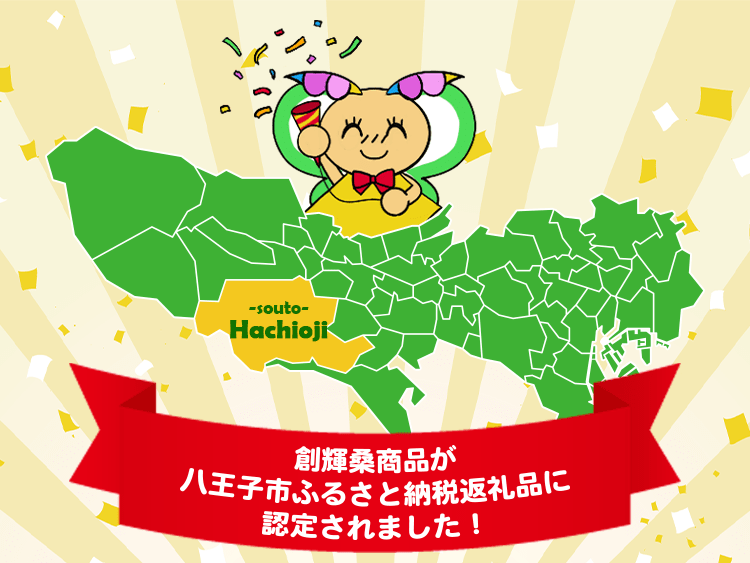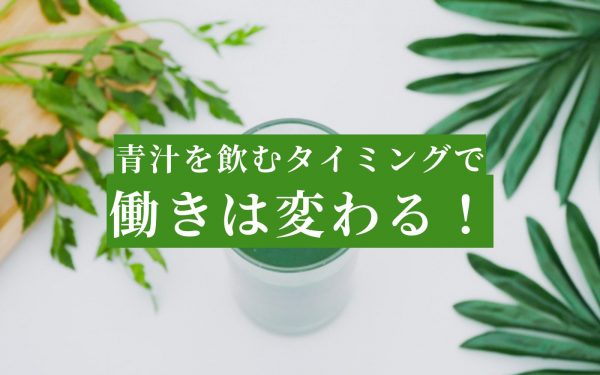漢方では桑の葉を中薬(副作用が少なく、ある程度病気を治す効果がある)として分類しています。
最新の研究でもその健康効果が明らかになり、注目の桑の葉。ここでは栄養と効果を紹介します。
漢方では桑の葉を中薬(副作用が少なく、ある程度病気を治す効果がある)として分類しています。
最新の研究でもその健康効果が明らかになり、注目の桑の葉。ここでは栄養と効果を紹介します。
桑の葉に含まれる栄養とは?

DNJ(1-デオキシノジリマイシン)

桑の特有成分で、体内の糖の吸収を緩やかにする働きがあります。化学構造がブドウ糖(グルコース)に似ており、小腸内の分解酵素がブドウ糖と間違えてDNJと結合することにより糖の吸収を遅らせます。
糖尿病対策やダイエット効果においても注目されている成分で、桑の葉はこの成分を自然界で唯一多量に含んでいる植物と言われます。
ビタミン・ミネラル
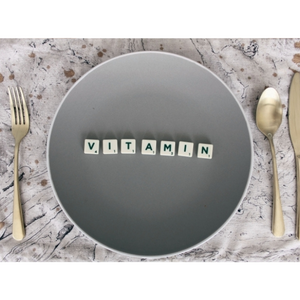
桑の葉には、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、ビタミンEなどのビタミン群と、カルシウム、鉄、亜鉛、マグネシウムなどのミネラルも豊富に含まれています。
なかでもカルシウムは牛乳10杯分もの含有量があります。その理由は、桑の葉の表面に植物の中で唯一、カルシウムを蓄える細胞があるからです。
このほか、食物繊維、抗ストレス作用のあるGABA(ギャバ)、高い抗酸化作用を持つポリフェノールの一種・ルチンなども含んでいます。
血圧への作用&副作用は?
 桑の葉に含まれる特有成分の働きで血糖ケアに期待が高まっておりますが、血圧への作用や副作用も気になりますよね。
桑の葉には、「血圧が高め」と指摘され、気になっている方にも嬉しい栄養素が豊富に含まれています。
それぞれいったいどのような効果があるのか具体的に見ていきましょう。
桑の葉に含まれる特有成分の働きで血糖ケアに期待が高まっておりますが、血圧への作用や副作用も気になりますよね。
桑の葉には、「血圧が高め」と指摘され、気になっている方にも嬉しい栄養素が豊富に含まれています。
それぞれいったいどのような効果があるのか具体的に見ていきましょう。
高血圧に作用する3大ミネラルが豊富
「カリウム」の作用とは?
高めの血圧を改善したい場合、栄養成分の視点から重要となるのが「カリウム」です。 カリウムは野菜や果物に多く含まれる成分で、塩分に含まれるナトリウムの排出を促す働きがあります。カリウムは「むくみ」の改善にも!
ナトリウム(塩分)の摂りすぎが、むくみの原因となることもあります。 カリウムを摂ることは、高血圧の予防となるだけでなく、むくみの解消にも有効と言えるでしょう。創輝の桑の葉にはカリウムが豊富
血圧だけでなく、むくみにも有効なカリウム。 桑「創輝」の葉に含まれるカリウムの量は「バナナの約7倍」と大変豊富です。血圧に作用する「カルシウム」
さらに、血圧に作用する栄養成分として注目したいのが、「カルシウム」と「マグネシウム」の2つです。 カルシウム不足は体の不調に繋がりますが、日本人が慢性的に不足している栄養素といわれています。 ほとんどのカルシウムは骨に含まれていますが、実は、血液や細胞などにも存在していて、血液中に含まれるカルシウムは「筋肉の収縮」に関わっています。カルシウムと血圧の関係
カルシウムが不足すると、骨からカルシウムを取り出して不足を補おうとします。 すると、血液中のカルシウム濃度が高くなり、余った分は血管の筋肉中に取り込まれます。 それにより、筋肉が収縮して血管が狭くなり、血流が悪くなってしまうのです。 その結果、心臓はより強い力で全身に血液を送らなくてはならず、血圧上昇につながります。創輝の桑の葉にはカルシウムが豊富

前述の通り、桑の葉の表面にはカルシウムを蓄える細胞があるため、含有量は大変豊富です。
そのため、桑「創輝」の葉には「牛乳の約33倍」ものカルシウムが含まれています。
「マグネシウム」の作用とは?
一方、マグネシウムには筋肉を弛緩させる働きがあります。 つまり、動脈を拡張させることで、血圧を下げる作用を担っているのです。 カルシウムとマグネシウムがバランスよく存在する場合は、血管の収縮と弛緩が正しく行われ血液の流れもスムーズになります。マグネシウム不足で起こる人体への影響
しかし、マグネシウムも必須ミネラルの1つでありながら不足しがちな成分です。 マグネシウム不足で起こりやすい体への影響には、下記のようなものがあります。- 高血圧
- 糖尿病
- 虚血性心疾患
- 神経疾患
- 不整脈
創輝の桑の葉にはマグネシウムが豊富

血圧に作用するだけでなく、体の中の酵素の働きを調整するという重要な働きを持つマグネシウム。
桑「創輝」の葉に含まれるマグネシウムの量は「ほうれん草の約4.6倍」と大変豊富です。
低血圧の人が桑の葉茶を飲んでも平気?
 桑の葉に含まれる成分が高血圧に効果的であるのは分かりましたが、反対に、低血圧の方が桑の葉茶や桑の青汁を飲んでも問題はないのでしょうか。
桑の葉に含まれる成分が高血圧に効果的であるのは分かりましたが、反対に、低血圧の方が桑の葉茶や桑の青汁を飲んでも問題はないのでしょうか。
あくまでも「食効」!薬ではありません
結論から申し上げますと、桑の葉には、正常値を超えるほど極端に血圧を下げてしまう作用などはありません。 あくまで「食効」のため、薬ではないからです。 そのため、低血圧の方でも問題なく桑の葉茶や桑の青汁を飲んでいただけます。より効果的に栄養摂取するなら「桑パウダー」がおすすめ
カルシウムやマグネシウムなど、桑の葉に含まれる成分は体を健康に保つために必要な成分です。 むしろ、不足しがちな栄養素を桑の青汁などでしっかり補うことができるのでおすすめです。 より効果的に栄養摂取をしたい方は、葉をまるごと粉砕して作られたパウダー状の「桑の青汁」を試してみてはいかがでしょうか。桑の葉が身体に与える良い効果

糖尿病予防
桑の葉に含まれている1-デオキシノジリマイシン(DNJ)という活性成分には、糖の吸収を抑制し血糖値を下げる働きがあるため、糖尿病の予防に効果的とされています。便秘改善効果
桑の葉に含まれている1-デオキシノジリマイシン(DNJ)によって小腸で吸収されなかった糖質は大腸で分解されます。 この時、発生する炭酸ガスや水素ガスによって大腸が刺激されて便通が改善されます。このほか、桑の葉の成分には動脈硬化の抑制にもつながる働きもあります。内臓脂肪型肥満予防
内臓脂肪型肥満とは、お腹周りの脂肪が過剰に蓄積しており「リンゴ型肥満」とも呼ばれている肥満のことを言います。不摂生が内臓脂肪型肥満の原因に!?
主に男性に多く見られ、生活習慣病とも密接に関わっています。 内蔵脂肪型肥満の予防には、バランスの良い食事や適度な運動、生活リズムを整えることなどが大切です。桑の葉で糖の吸収を抑えます!
また、「インスリン」の過剰分泌も脂肪が増える原因となるので注意が必要です。 桑の葉の特有成分には、食事で摂取する余分な糖の吸収を妨げる働きがあります。 そのため、食後の血糖値の上昇が穏やかになり、インスリンの過剰分泌の抑制につながります。桑の葉習慣で血圧に悩まない日々を!
 薬を服用するよりも、なるべく自然のもので高血圧の予防をしたいと考えている方には、普段の食事に桑を取り入れるのがおすすめです。
八王子産の桑「創輝」は農薬不使用の有機栽培で育てられた安心・安全な桑の葉。大きく、濃い緑の葉が特徴で、味はうま味とほのかな甘みがあります。
パウダーを溶いて飲むのはもちろん、料理やお菓子の隠し味としても使えます。「創輝」のパウダーは素材も味を邪魔しないので、毎日好きなアレンジで楽しめます。
実際に、毎日の食生活に創輝の桑の青汁や桑の葉茶を取り入れている方からは、「血圧が安定した」「正常値になった」など血圧改善の嬉しいお声を多数いただいております。
気になる方はぜひ一度ご連絡くださいね。
薬を服用するよりも、なるべく自然のもので高血圧の予防をしたいと考えている方には、普段の食事に桑を取り入れるのがおすすめです。
八王子産の桑「創輝」は農薬不使用の有機栽培で育てられた安心・安全な桑の葉。大きく、濃い緑の葉が特徴で、味はうま味とほのかな甘みがあります。
パウダーを溶いて飲むのはもちろん、料理やお菓子の隠し味としても使えます。「創輝」のパウダーは素材も味を邪魔しないので、毎日好きなアレンジで楽しめます。
実際に、毎日の食生活に創輝の桑の青汁や桑の葉茶を取り入れている方からは、「血圧が安定した」「正常値になった」など血圧改善の嬉しいお声を多数いただいております。
気になる方はぜひ一度ご連絡くださいね。