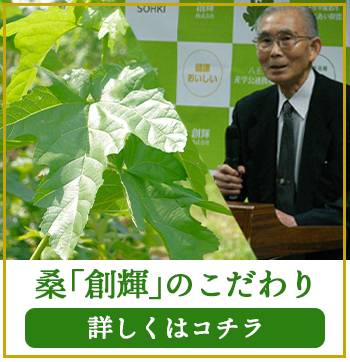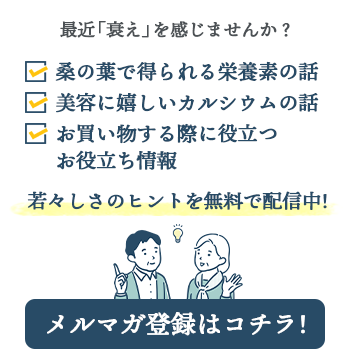近年、その効力が話題の「桑の葉」。
実はその歴史は古く、古の人々もそのパワーを期待して体に取り入れていました。
桑の葉の歴史を知れば、そのパワーを実感できるはず。
近年、その効力が話題の「桑の葉」。
実はその歴史は古く、古の人々もそのパワーを期待して体に取り入れていました。
桑の葉の歴史を知れば、そのパワーを実感できるはず。
目次
桑の歴史とは?
桑は養蚕には必要不可欠な植物
桑は絹を生産するために必要な蚕が唯一食べる葉で、養蚕には欠かせない植物です。 蚕の繭から絹の生糸を作る「養蚕」は、今から5~6千年ほど前の中国・揚子江流域で始まり、日本には弥生時代に稲作とともに伝えられたと言われています。 化学繊維が生まれるまでは、生糸を作る養蚕業は大きな産業でした。そのため桑の栽培も全国的に広がりました。★-1024x720.jpg) (写真提供:八王子市、八王子市教育委員会、日本遺産「桑都物語」推進協議会)
(写真提供:八王子市、八王子市教育委員会、日本遺産「桑都物語」推進協議会)
人間の健康とも深い関わりのあった桑
桑の栽培が全国的に広がったことで、一般にも広く知られるようになった桑。しかし、それは繭を作る「蚕の餌」としてであり、人が口にするものとしての認知は逆に低くなってしまいました。 元来、桑は人間の健康とも関係の深い植物でした。桑の葉茶の歴史とは?
薬草として重宝されてきた
桑の効能は中国最古の医学書にも
桑の葉を日陰で乾かした物を「神仙茶」と言い、「不老長寿の妙薬」として中風や滋養強壮に用いられて重宝されてきた歴史があります。日本では鎌倉時代に「長寿の薬」として
桑に関して記載が残る日本書物では、「はぐは」として桑が紹介されており、冷えや腹痛の症状が緩和されたと記述が残っています。 他にも、桑粥や桑湯が紹介されているなど、様々な書物の中で桑が取り上げられています。多くの漢方薬に用いられた
漢方では桑の根を桑白皮(ソウハクヒ)、桑の葉を桑葉(ソウヨウ)、桑の果実を桑椹(ソウジン)と言い、生薬として根・葉・果実の全てが薬の原料として利用されています。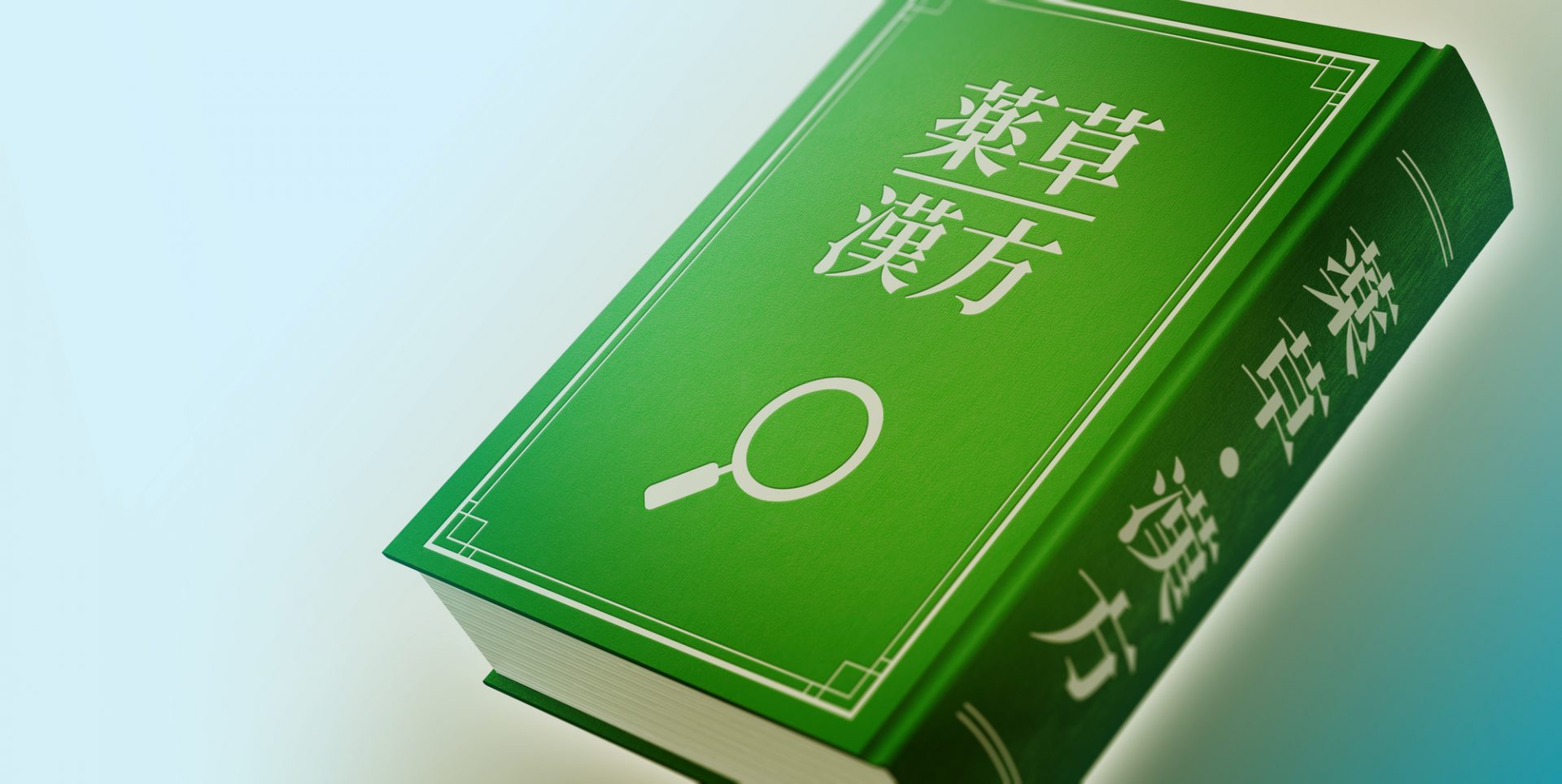
桑の葉キャンペーンを行ったのは禅僧?
鎌倉時代の医書に書かれた桑の効能
「茶は養生の仙薬なり」で始まるのは、鎌倉時代の代表的な医書の1つ「喫茶養生記」。禅僧・明庵栄西(1141-1215)が記し、鎌倉幕府3代将軍・源実朝に献上したことで知られています。 上下二巻からなるこの書の下巻は「五種の病を桑をもって治療する」という内容で、桑の飲み方や効能が書かれています。 五病とは、「飲水病、中風、拒食、瘡、脚気」のこと。現在の症状では飲水病=糖尿病、中風=脳梗塞の後遺症、拒食=食欲不振を意味します。中国から伝わった飲茶のひとつ
栄西は中国・宋での留学中に見聞、経験した茶、および桑について帰国後に伝え、日本では栄西以降、本格的に飲茶の習慣が普及したと言われています。
緑茶の代わりだった桑の葉茶
現在では身近によく飲まれている緑茶などのお茶は、茶の木の茶葉が利用されています。 しかし、昔は茶の木は高級品であったので、庶民は身近にある木の葉を利用してお茶の代わりとして飲んでいた歴史があります。 そのお茶の代わりのひとつが、桑の葉茶でした。桑の葉のパワーを最大限に
古の人々にも知られていた桑の葉のパワー。現在ではさまざまな研究によって、含まれる栄養素や効能がより詳しく明らかになっています。健康に良いと注目を集める桑の葉茶
最近では桑の葉茶がもつ栄養や効能の研究が認められ、桑の葉特有の成分である1-デオキシノジリマイシンに、 食後の血糖値上昇抑制効果があると研究で発表されています。 その他にも、カルシウム、鉄、亜鉛、食物繊維なども豊富に含有されており、栄養素の高い植物として大きく注目が集まっています。